この記事では、ライカのレンズを殆ど使ってきた中で、オススメしたい50mmのレンズを独断と偏見でご紹介していきたいと思います。
なお、ライカレンズ初心者のための35mmのオススメは下記で紹介しています。

ライカ沼の醍醐味、オールドレンズのオススメはこちらにまとめています。

ライカと50mm
50mm=王道
一眼レフカメラの標準画角は50mmと言って間違いありません。
標準だから何?って感じもあるかもしれませんが、標準の良さはやはり、それ一本でいける画角の使いやすさと、明るいレンズも安価で選択肢も多いというラインナップの豊富さだと思います。
最近は28mm付近が主流のスマホの写真に見慣れていることもあり、この標準という感覚も広角寄りになってきていますが、、
話は戻って、私が大好きなライカはM2から現在の最新機種まで採用されている視野率のファインダーでは35mmフレームが非常に使いやすくなっています。
なので、以前に私は35mmがライカの標準だ!と声高らかに記事を書いています
しかし、今回購入したM3は、50mmブライトフレームに最適化された広視野率のファインダーを採用しているので、35mmは非対応になっていますし、M3のファインダーに惚れて、それ以外の機種でもマグニファイヤーというものを用いることで視野率をM3に近づけています。

この50mmという画角の歴史を探ると、M3以前のライカは、1920年頃に登場した初代のA型アナスチグマートから採用されていました。
標準画角=50mmというのはライカが生み出し、ライカにとっても50mmは伝統的で特別な画角です。
そのため、最近は広角レンズの種類の方が豊富になってきていますが、50mmは古いレンズを含めれば最も多くの種類があります。
Leicaのレンズ
まずはライカの純正レンズを見ていきます。
Elmar 50mm (全モデル)
ライカの、原点となるレンズ。

Leica Elmar f2.8/5cm
数ある沼の中でも最も深い沼の一つ、ライカ沼。
そんなライカ沼の最後はこのエルマーに行き着くなんて言われています。
それ故に、今の私ではその魅力を語りきれない程に奥が深いレンズです・・・
エルマーはテッサータイプの3群4枚というシンプルなレンズ構成で、原点と書いたように、1920年頃の初期のA型から採用されるライカの元祖標準レンズです。
古いから、写りは大したこと無いんじゃないの?と思うかもしれませんが、そんなことはありません。
光学技術は写真カメラの生まれる以前からある学問で、すでに成熟していたわけです。
その当時はコンピューターによる、写真レンズに最適化された複雑な設計は勿論、工作技術やコーティング技術もありません。
しかし、その写りは無理のない設計のおかげで、歪曲収差が少ない事に定評があります。
現代の高性能レンズと比べてしまうと、コントラストやシャープネスなどの描画性能は劣るかもしれません。
ただ、レンズの価値とは、シャープネスだけではありません。
確かに性能の指標としては、重要な要素で、デジタルで撮影すれば、そのレンズの限界は私達アマチュアでも十分に認識できます。
ただ、このシャープネスや収差というのは、例えば、絵画の保存や、文字などの拡大印刷といった記録要素において重要なものですが、今日の写真撮影においては、さして重要な要素ではありません。
この全てが写りすぎないレンズを手に取り、その眼で世界を切り取っていく。
そんなフォトグラファーになれたら凄くかっこいいですよね。
エルマーは1920年代にカメラ本体への固定式として採用され、1930年に交換式のものが誕生、そして、新しいものは2010年頃まで生産されてきました。
交換式で言えば、最初期の1代目、50年代にのM型の登場と同時期に登場した2代目、そして、60年代に廃盤ののちに30年の時を経て復活した3代目があります。
f値は当初は3.5で、2ndの途中から2.8に明るくなりました。
そして3rdでは光学系も一新され、性能が向上しました。
玉数が多いのも特徴で、美品でも価格は10万円以下で手に入りますし、初代・2代目であれば3万円台から入手が可能です。
余談ですが、私の所持する2代目時代の沈胴レンズは絞りが何と16枚もあります。
贅沢な作りです。
絞り羽根からも分かるように、本体も仕上げの良さは素晴らしく、日本メーカーには無い作りの良さが道具としての使用する快感を感じさせてくれます。
(ちなみに私は苦手なレンズです。笑)
Summar 50mm f2
このズマールは、今のすべてのライカのレンズの原型になったといっても過言ではありません。
詳しくは下の記事で記載していますが、ダブルガウス型という今ライカが標準的に用いているレンズ設計を最初に取り入れたモデルです。

今ではその柔らかさが味わい深く、私は非常に好きです。
また、製造数も多く、おそらくライカの50mmでは最も安く購入することができます。
Summicron 50mm f2 1st

Summicron f2/5cm 1st(沈胴)
ズミクロンは現行で4代目まで出ており、どのモデルを選定するか悩みました。
多分どれを手に撮っても後悔はないと思うのですが、あえて初代モデルを推したいと思います。
その理由は、描画性能の高さです。
エルマーではスペックが全てじゃないとかいいながらも、この50mmのズミクロンの特徴はその描画性能の高さにあります。
その解像度は、なんと現行のズミクロンM 50mmに匹敵することが分かっています。
このレンズは、伝説のライカ使いアンリ・カルティエ=ブレッソンが最後まで愛したレンズでした。
古くから使い慣れたレンズということもあると思いますが、最も偉大なライカ使いのブレッソンはこのレンズを最も優れたレンズだと認めていたのでしょう。
レンズ構成は6群7枚の変形ガウスタイプで、1枚目と2枚目の間に空気の層を設けた構成が特徴的で空気レンズと呼ばれています。
その凝った作りで、おそらくレンズの組み込みは相当な難しさだったんだろうと思います。
次のモデルからは、通常のガウスタイプとなりました。
そんな、F2というスペックの割には凝りに凝っていたこのズミクロンも、とくに沈胴タイプは安価で入手できます。
しかし、沈胴タイプのデメリットとして、精度が維持しづらいということで、状態が悪いものも多くあります。
お墨付きの描画性能は固定鏡胴タイプですが、沈胴も状態のいいものを選べば問題ありません。
無限遠で、解像度が高いものを選ぶのが良いのではないかと思います。
安価な固定鏡胴があれば、迷わず飛びつくべきでしょう!
SUMMILUX-M f1.4/50mm ASPH.

SUMMILUX-M f1.4/50mm ASPH.
この上にはAPO-SUMMICRONや、NOCTILUXというレンズがありますが、だからといってこのズミルックスが劣るかというとそんなことはありません。ズミルックスは世界の宝です。
この現行のズミルックスは、被写体が浮き出る解像力となめらかなボケが最高に美しいレンズです。
初代の上質な鏡胴や、2代目の空気レンズ採用モデルなど、ズミルックスも魅力的なモデルがたくさんあり、私は初代のモデルが好きですが、使いやすさで言えば、この現行品に軍配が上がります。価格も今では殆ど変わりません。
Cosinaレンズ
35mmでは、コシナ(フォクトレンダー、ツァイス)のレンズは、本家のライカが強すぎてほとんど紹介できませんでしたが、50mmはライカに劣らない本当にいいレンズが沢山あります。
Carl Zeiss Planar 50mm f2 ZM

Carl Zeiss Planar 2/50 ZM
標準レンズの王様です。
それはなぜかと言うと、その昔カールツァイス謹製のコンタレックスという弩級カメラがありました。
コンタレックスはツァイスが自分でカメラを作っていた頃の民生用の本気カメラです。
そのコンタレックスの標準レンズとして採用されていたのが、Planar 50mm f2でした。
なんで王様かというと、コンタレックスのレックスは王様という意味で、王様に採用されている標準レンズだから標準レンズの王様です笑
コシナツァイスには、レンズ画像のように指掛けとして気持ちばかりの突起が付いています。
ライカやVoigtlanderのレンズには人差し指でフォーカスレンズが操作できる大きなものがついているのですが、それに比べると正直操作は若干しづそう・・・
そもそも、従来のツァイスが生産していたレンジファインダーのコンタックスレンズには、この指掛けは付いていませんでした。
なので、私はコシナがレンジファインダー レンズには指かけを付けたかったがために、カールツァイスが認めてくれる範囲で、妥協的に付けているモノだと勝手に思っていました。
しかし、コンタレックスのレンズを見てみましょう、、、

コシナさんすみませんでした。
この突起は、王のレンズにのみ許されていた由緒正しきものでした。
なので、この突起は由緒正しきツァイスの仕様で、レンジファインダーにこの突起を採用したコシナと現代のツァイスを私は称賛したいと思います。
スペックを見ていくと、このレンズはプラナーの名前を冠しており、ダブルガウスタイプの4群6枚のレンズ構成となっています。
ダブルガウスの特徴は、歪曲収差、像面湾曲の少なさがあります。
解像は中心付近は良好で、周辺に行くと、若干甘めになります。
描画のイメージとしては、よく写る優等生。
癖がなく、破綻が少ないので、非常に扱いです。
ニコン時代では、Planar 50mm f1.4 zf.2を常用としてとにかく愛用していたので、個人的には間違いないと思います。
Carl Zeiss C Sonnar 50mm f1.5 ZM

Carl Zeiss C Sonnar 1.5/50 ZM
ゾナータイプのレンズ構成を持ち、先ほどのプラナーよりも1段近く明るいf1.5の大口径レンズです。
このレンズの特徴は、その名にもある’C’にあります。
C SonnarのCとは、Classic,Compactの頭文字からきており、その名に恥じぬ素晴らしいレンズになっています。
まず、’コンパクト’なサイズというのは、全長にあります。
このレンズの全長は38.2mmです。
一方で、プラナーはこのレンズよりも暗いにも関わらず、全長43.5mmあります。
ちなみに、ライカのズミクロンはプラナーと同様の43mm、f1.4でこのレンズと違いズミルックスは46mmであることを考えるといかにこのレンズがコンパクトかが分かると思います。
ライカ自体が薄型のカメラなので、見た目的にもコンパクトなレンズの方がいいでしょうし、カメラをカバンに突っ込むことを考えると、常用レンズは短いほど使いやすくなりますので、かなりの重要ポイントです。
そしてもうひとつの’クラシック’ですが、これは1932年に開発されたコンタックス用Sonnar 50mm f1.5の光学設計をほぼそのまま採用しているようです。
しかし、最新のT*コーティングにより、コントラストやフレアゴースト等が改善されているので、この時代の絵作りが、これらのデメリットなく味わう事ができるレンズです。
先ほどのプラナーも決して最新の設計とは言いませんが、コシナの公式ページに公開されているMTFや各種収差を真面目に見ると、高価なこのレンズの方が実は劣っているのです。
その為、星景撮影のような緻密さを求める用途には向きません。
しかし、レンズの魅力はスペックだけでは語れない所が面白いんです。
このレンズの描画の特徴は美しいボケ。とにかくボケに定評があります。
ですから、ボケのようなスペックに反映されない部分は個人の好みによる所が強く、万人向けというよりは、このアプローチに魅力を感じた人が取り憑かれる系のレンズだと思います。
確実に言えることは、コンパクトだが、高価な割にシャープネスや収差は良くないということです。
また、絞りの変化でフォーカスシフトが起きるレンズなので、EVFを使わない限り、光学ファインダーでは絶対にジャスピンが来ません。
ピクセルを拡大して見てジャスピンを求める人用のレンズではありません。
しかし、 2004年に発売されたこのような高くてデメリットがあるニッチなレンズが未だに新品で買えることを考えると、スペックでは測れない人気があることは認めざるを得ないでしょうね。
このレンズはロシアの銘玉jupiter-3とjupiter-8がそっくりで安価なので、そちらを試してみてもいいかもしれません。
Voigtlander Nokton Vintage Line 50mm f1.5 Aspherical

Voigtlander Nokton Vintage Line 50mm f1.5 Aspherical
くびれが特徴的なこのレンズは、1951年に発売された同名レンズを再現しています。
しかし、光学設計は最新で、後玉には高価な非球面レンズが採用されています。
非球面レンズの分かりやすい特徴は、開放からのシャープネスの高さと、収差の少なさです。
その描画は、癖が少なく特性も良好なため、万人にお勧めできます。
非球面採用で10万を切る価格は、かなりお買い得だと思います。
ただ、それだけでは、私はここにあえて紹介はしていません。
このレンズの魅力はその個性的な外装にあります。
このくびれたフォルムは好き嫌いが分かれる所かと思いますが、私が素晴らしいと感じているのは、カラーによって外装の素材を変えている所です。
これは、私の所持しているSUMMICRON-M 35mmなど、ライカも一部のレンズで行っています。
シルバーは真鍮で、ずっしりと重みを感じられることと、重厚感のある操作感が特徴です。
一方で、ブラックはアルミで、軽量なことと金属によるかっちりとした操作感が両立されています。
個人的に言えば、圧倒的に真鍮派。
なので、真鍮をラインナップしてるこのモデルはかなり評価したいです。
真鍮崇拝派なので、ツァイスも真鍮で作って欲しいなぁ。。笑
(追記)2021年リニューアルしました

M3用に私が今回購入したレンズは・・・
購入したレンズはコチラ!!

Leica M3 + Carl Zeiss C Sonnar 1.5/50 ZM
今回激戦を勝ち抜き私のもとに迎え入れることとなったレンズは、Carl Zeiss C Sonnar 50mm f1.5 ZMです
理由はシンプルで、描画もサイズも明るさのバランスが最も良かったからです。
フィルムカメラは、そもそも解像度という概念がありませんが、スキャンしてデジタル画面で見ればその粗さ(粒子の粒感)は否めません。
フィルムカメラはディスプレイ上での再現性はデジタルで劣るかもしれませんが、その雰囲気とか空気感を残す能力に長けています。
そのため、フィルムでは対象をより美しく見せることが望ましく、そのためには違和感のないボケが重要です。
また、常用ですから、そのサイズ感も重要ですよね。

Elmar / C Sonnar / 7artisans 50mm
わずかな差かもしれませんが、取り回しのしやすさはこれだけで全然変わります。
これで、f1.5の明るさがあるのであれば御の字です。
ISO400あれば夜でも使えるほど明るいです。
まとめ
50mmは歴史のある画角で、今回ご紹介したもの以外にも星の数ほど存在しています。
というのは、戦後ライカコピーが日本やロシア、アメリカ等で大量に生産優れたため、それに合わせた数多くの50mmLマウントレンズが合わせて生産されたからです。
今回紹介したものは、そういった量産型の特徴が少ないものやコスパだけのものとは異なります。
どれも選んで後悔しないような、メインとして心の底から気に入って愛用できるレンズになること間違いありません。
Mマウントでは基本的に28mmや35mm常用の方が多いかもしれませんが、50mmは被写体のクローズアップも広角より得意ですし、ポートレートも距離感よく撮影をすることができるのでお勧めです。
ぜひM3以外のM型をお使いの方も、2本目以降に50mmのレンズ、検討してみてはいかがでしょうか。
なお、拗らせた方は、50mmには深い沼が待っていますのでお気をつけください…












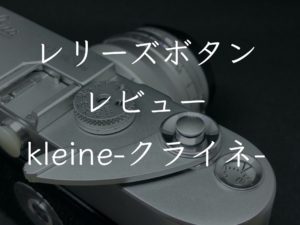



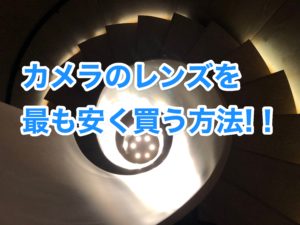
コメント